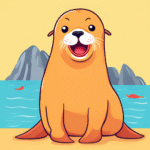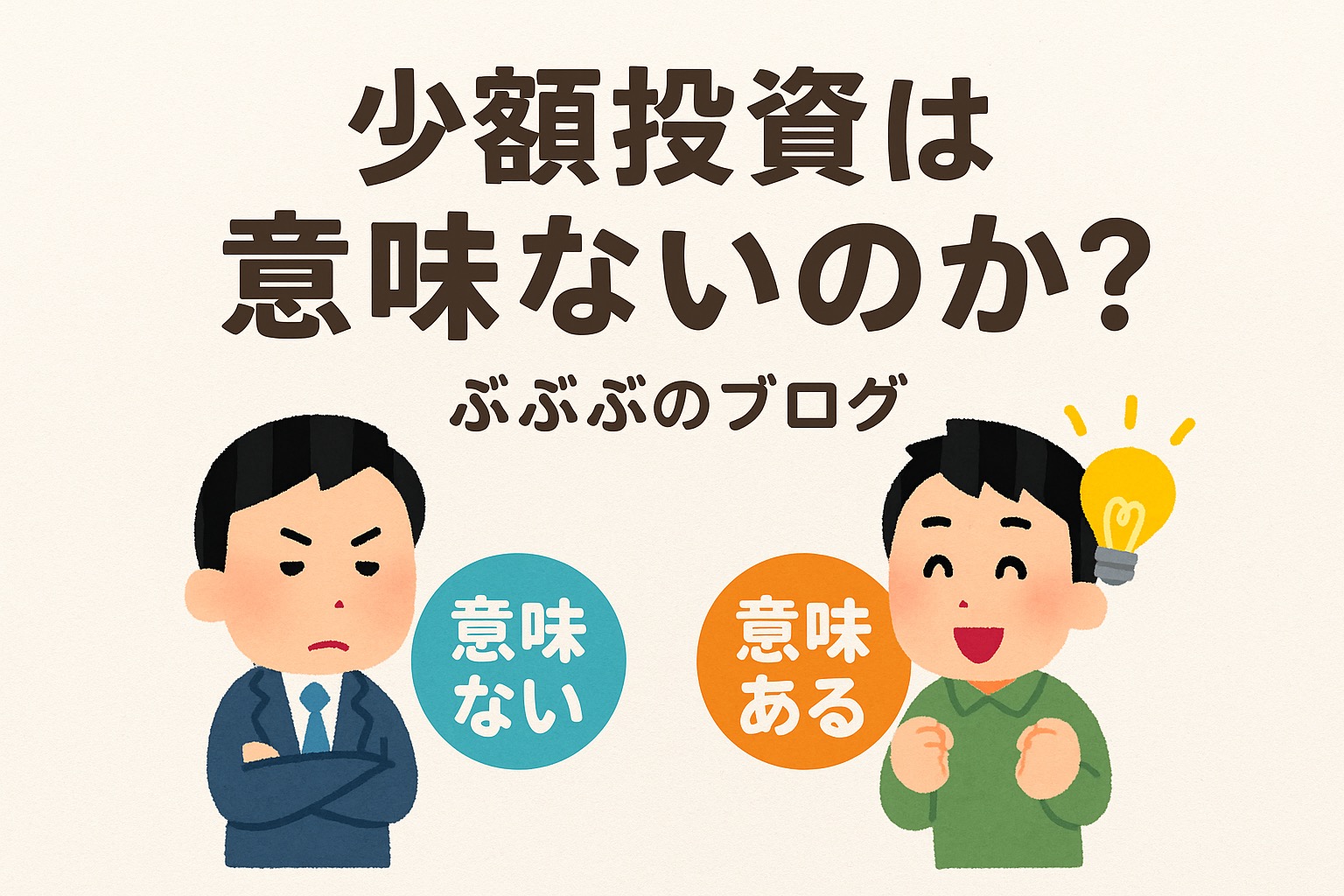iDeCoのルールが変わる!そもそもiDeCoって何?やる必要はあるの?

目次
📌 この記事はこんな人におすすめ
- iDeCoの最新ルール改正ポイントを簡単に知りたい人
- 掛金上限や加入年齢の変更が自分にどう影響するか気になる人
- iDeCoの受け取り方(出口戦略)を見直したい人
- そもそもiDeCoってなに?って人
⏰ 所要時間:3分

どうもぶぶぶです。
今回は 「iDeCoのルールが変わる!そもそもiDeCoって何?やる必要はあるの?」 というテーマでお届けします。
この記事を読んでくださっている方の中には、

iDeCoって難しそうだな…そもそもやる必要あるのかな?
こんな疑問を持っている方も多いと思います。
実際、iDeCoは掛金が全額所得控除になったりと税金優遇制度が魅力的なところもある一方で、受け取り時には税金がかかったりと出口戦略が難しい…なんてこともあります。
そこで今回は、iDeCoとは何か、やるべきかどうか、そして新しく決まったルール改正のポイントを、私の主観も交えながらわかりやすく解説します。
この記事を読み終えれば、iDeCoに関する疑問がスッキリ解消するはずです。
ぜひ最後までお付き合いください。

それでは本編へどうぞ!
そもそもiDeCoってなに?
「iDeCo」という名前は、英語の individual-type Defined Contribution pension plan(個人型確定拠出年金)の頭文字などを組み合わせたものです。
簡単にいえば、自分で積み立てる年金制度で、そのお金を株や投資信託などで運用して、将来の老後資金をつくっていく仕組みです。
掛金は全額所得控除になり、運用益も非課税。受け取り時にも税制優遇があります。
ただし、60歳までは原則引き出せないため、老後資金専用の制度と考えるのが基本です。

じゃあ、急にお金が必要になってもおろせないってことだよね?それって不便じゃない?

そういうことだね!不便だけどだからこそ税金の優遇が大きいんだよ

なるほど…

だからこそ、NISAよりも慎重に始める必要があるんだ
いつでも引き出せるNISAと違い、iDeCoは引き出すことができません。
そのため、自分のライフプランをしっかり考えたうえで、加入するかどうかを判断することが大切です。
iDeCoの掛け金について
今度はiDeCoの掛け金について説明をします。
iDeCoで毎月拠出できる金額(掛金上限)は、年収ではなく職業区分によって決まります。

職業区分ってなに?

iDeCoでは、自営業、会社員、公務員、専業主婦(夫)…っていう具合に、働き方や加入している年金制度によって「どんな働き方をしているか」でグループ分けしているんだ。それを「職業区分」って呼んでるんだよ

それによって掛けられる金額が違うのね

そのとおり。だからまずは自分がどの職業区分なのかを把握することが、iDeCoを始める第一歩なんだ!
DeCoで毎月拠出できる金額(掛金上限)は、年収ではなく職業区分によって決まり、同じ職業区分であれば、年収が300万円でも1,000万円でも、掛金上限は同じです。
こちらが簡易的ですが、一覧表になります↓
| 職業 / 区分 | 掛金上限(月額) | 年間掛金上限 |
|---|---|---|
| 自営業(第1号被保険者) | 68,000円 | 816,000円 |
| 会社員(企業年金なし) | 23,000円 | 276,000円 |
| 会社員(企業年金あり) | 20,000円 | 240,000円 |
| 公務員 | 20,000円 | 240,000円 |

私は会社員で、確か企業年金があったと思うから月の掛金上限額は20,000円ね!

僕の会社は企業年金がないから23,000円が上限額になるんだ
iDeCoの掛け金は最低5,000円になり、そこから1,000円単位で上限額までかけれます。
iDeCoのメリットデメリット
先ほども説明しましたが、 iDeCoには60歳までは原則引き落とせないという大きいデメリットがあります。ですが、その大きいデメリットがあるからこそ大きいメリットを受けれるんです。

今度はメリットデメリットを一覧表で紹介します
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 掛金が全額所得控除(節税効果が大きい) | 60歳まで原則引き出せない |
| 運用益が非課税(通常の投資より有利) | 受け取り時に税金がかかる(退職所得控除や公的年金等控除の範囲内なら非課税可) |
| 受取時も税制優遇あり(一時金なら退職所得控除、年金形式なら公的年金等控除) | 受け取り方によっては税負担が増える(出口戦略が必要) |
| 少額から始められる(月5,000円〜) | 掛金の変更は年1回しかできない |
| 長期運用により老後資金形成しやすい | 元本割れのリスクがある(運用商品による) |
| 自営業者は国民年金の上乗せになる | 口座管理手数料がかかる(年間2,000円〜) |

こう見るとメリットデメリット色々あるのね

だからこそメリットデメリットをしっかりと把握して、自分の中で納得してからやることをオススメするよ
メリットデメリットとさまざまですが、NISAと同じく元本割れのリスクがあるので、余剰資金でやるようにしましょう。
2028年からの新ルール
ここまで iDeCoのルールを解説してきましたが、2025年6月に改正法案が可決・成立したことで、2028年から新ルールが始まります。
「結局どう変わるの?」という方のために、押さえておきたい3つの改正ポイントを分かりやすく解説します。
① 掛金の上限アップ
今回の改正の中で一番大きなポイントです。
- 自営業など:月6.8万円 → 月7.5万円
- 会社員・公務員:月2〜2.3万円 → 月6.2万円
さらに、企業型年金のある会社員にあった「iDeCoは月2万円まで」という上限も撤廃されます。
企業年金があっても、より多く積み立てられるようになるのは嬉しい変更です。
② 加入できる年齢が延長
これまで65歳未満までだった加入可能年齢が、一定の条件を満たせば70歳未満までに延長されます。
受け取り開始は変わらず60歳からですが、
- 老齢基礎年金
- iDeCoの老齢給付
のいずれも受け取っていなければ、最長70歳まで掛金を拠出できます。
定年後も働きながら積み立てを続けたい人にとっては、大きなメリットです。
③ 受取時の“10年ルール”に注意
こちらは利用者によっては不利になる改正です。
これまであった「5年ルール」が、「10年ルール」に変わります。
旧ルール(5年)
- 60歳でiDeCo一時金 → 退職所得控除で節税
- 65歳で会社の退職金 → 退職所得控除でまた節税
→ 控除が2回使える
新ルール(10年)
- 60歳でiDeCo一時金 → 控除OK
- 65歳で退職金 → 10年経っていないので控除NG
→ 税金負担が大きくなる可能性
出口戦略(受け取り方の設計)を考え直す必要が出てきます。
主な対策は以下の通りです。
- 退職を70歳にずらし、60歳でiDeCo、70歳で退職金を受け取る
- iDeCoを年金方式で受け取り、退職金は通常通り受け取る
- iDeCoの掛金を減らす
どれが最適かは人によって異なります。
まとめ:改正ポイントは3つ
- 掛金上限が大幅アップ
- 加入年齢が70歳まで延長
- 5年ルールが10年ルールに変更(節税しにくくなる)
なお、「60歳まで引き出せない」ルールは変わりません。

この新ルールを元に、ぶぶぶ的な優先度はこちら
- まずは新NISA
- 余裕がある人はiDeCoに加入するのもあり
といった温度感になります。
僕自身も旧NISAで積み立てをしていた時は余剰資金があったため、iDeCoに上限額を入れていました。
ですが、新NISAが始まったことでそちらに全力投資しているため、iDeCoは一旦ストップしています。
そもそも僕はセミリタイアを目指しているので、iDeCoが本当に意味をなすのか微妙だなとも感じています。
正直、出口戦略を調べたり考えたりするのがめんどくさい、というのが本音です。
なので結論としては、普通の人はiDeCoを無理にやる必要はないと思います。
新NISAで毎月30万円投資できて、それでもまだ余剰資金がある人が検討するくらいの温度感でいいでしょう。
最後に、今回の改正で、iDeCoはより使いやすくなりましたが、受け取り方の設計はさらに難しくなりました。
掛金や受取時期の組み合わせによっては、将来の手取り額が数十万〜数百万円変わる可能性があります。
自分自身のライフスタイルや余剰資金をしっかりと把握し、無理のない投資をしましょう。
ではでは。